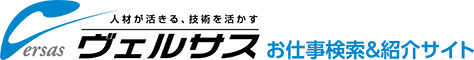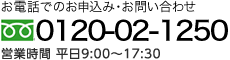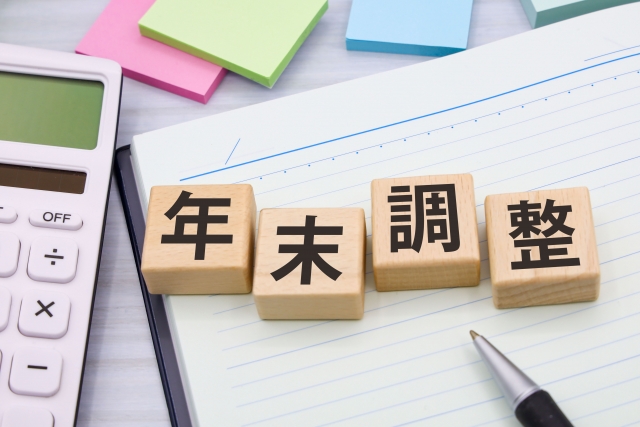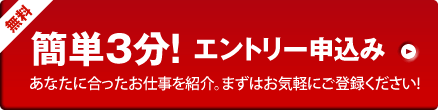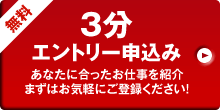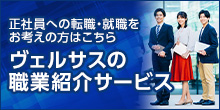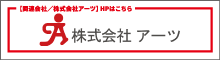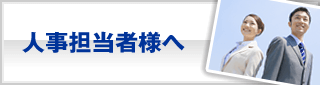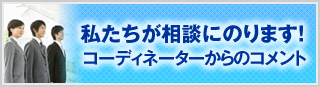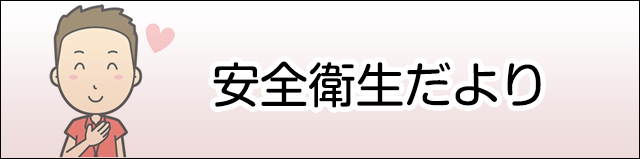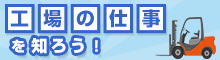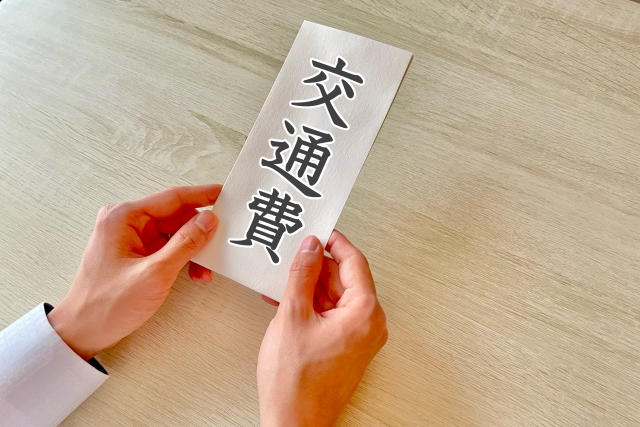
こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
パートやアルバイトとして働いており、会社から交通費を支給されている場合には、給与所得と同様に課税対象になる他、扶養に影響を与えるケースがあります。
扶養と交通費の関係性を理解していないと、扶養から外れてしまう可能性もあるので、しっかりと理解しておく必要があります。
今回は、扶養に関わる年収と交通費の関係や非課税限度額について解説していきます。
■2種類ある扶養について理解しよう
交通費の取り扱いを理解するためにも、前提となる扶養について理解しておく必要があります。
扶養には、税法上と社会保険上の2種類が存在します。
それぞれについて解説していきましょう。
・税法上の扶養
所得税や住民税の控除を受けたいと考えるなら、税法上の扶養範囲内に年収を抑えなければいけません。
その場合、年収を103万円以下に抑える必要があります。
ただし、住民税は住んでいる地域によって非課税範囲に違いがあるので、100万円以下の年収だとしても税金が発生するケースもあります。
詳細は、居住している役所に問い合わせてみましょう。
また、被扶養者の年収が103万円以下だと配偶者や親など、扶養する人の所得から一定の金額を控除できるため、扶養者が納める税金も少なくなります。
ただし、被扶養者の年収が103万円以上になれば控除の対象から外れてしまうので、双方の税負担が重くなる点に注意してください。
・社会保険上の扶養
扶養者が加入する社会保険のうち、健康保険の被扶養者になることを社会保険上の扶養と言います。
社会保険の被扶養者であれば、健康保険料を納める必要がないので負担が少なくなります。
しかし、条件を満たしてしまうと社会保険への加入が義務付けられます。
加入するとなれば、健康保険料だけではなく厚生年金保険料も引かれるので、手取りが少なくなる可能性があるでしょう。
社会保険上の扶養を抜ける条件としては、本人の年収が130万円を超えた場合です。
しかし、社会保険の加入条件は年々変化しており、適用範囲が拡大しています。
働いている会社の規模や働き方によっては、年収106万円が目安となります。
その場合は、年収が106万円を超えてしまうと社会保険に加入することになるため、税負担が増えてしまいます。
■交通費は年収に含まれる?
税法上や社会保険上で扶養範囲は異なります。
それぞれの扶養範囲内で働くためには年収を計算しなければいけません。
しかし、その際「交通費はどうなるのか」と疑問を持つ方もいます。
ここからは、交通費の取り扱いについて解説していきましょう。
・税法上の扶養では交通費は含まない
税法上の扶養では交通費は所得とみなされないため、年収には含みません。
ただし、非課税限度額を超えた分は所得にカウントされてしまいます。
しかし、パートやアルバイトで交通費が非課税枠を超過するのはレアなケースです。
勤務先によっては非課税分を超えないように調整しているケースも多いため、気になる場合は勤務先に確認してみてください。
・社会保険上の扶養では年収によって異なる
社会保険上では、106万円相当と130万円を越えた場合で交通費の取り扱いが異なります。
社会保険の適用拡大に伴って勤務先が該当した場合、年収106万円相当で社会保険への加入が必要です。
この場合は、交通費は年収に含まれません。
各種手当や賞与も含まずに算出するので覚えておきましょう。
一方、年収130万円を超えると交通費は収入として扱われてしまいます。
定期券の現物で支給されている場合でも、金額換算して含めなければいけません。
そのため、年収を128万円に抑えていた場合でも、年間3万円が交通費として支給されていれば、年収が130万円を超えてしまうので社会保険料を支払う必要があります。
■交通費の非課税限度額について
前述したように、年収103万円以下であれば交通費は年収に含まれませんが、非課税枠が設けられています。
活用する手段によって非課税枠が異なるので、それぞれを解説していきましょう。
・公共交通機関を活用するケース
電車やバスといった公共交通機関を活用して出勤する場合の非課税限度額は月15万円です。
15万円以下であれば非課税となり、超過すれば課税対象となります。
しかし、多くの会社では就業規則で交通費の支給上限が定められているので、月15万円を超えるケースは稀です。
・自家用車やバイクを活用するケース
自家用車やバイクで会社まで通勤している方もいるはずです。
その場合、非課税限度額は勤務先の距離によって細分化されています。
| 通勤距離(片道) | 1ヶ月あたりの限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
非課税限度額を超えて通勤手当を支給する際には、超過している部分の金額が給与として課税される仕組みです。
そのため、学生でアルバイトをしており、年収が100万円で1ヶ月の通勤手当で3,000円を支給されている場合、年間で36,000円支給されていることになります。
その場合は、年収が103.6万円となってしまうので、所得税の支払いが生じてしまいます。
親も扶養控除が受けられなくなるため、納税額に大きな影響を与えてしまいます。
■交通費の受け取り方に注意!
扶養範囲内で働きたい方に関しては、交通費の受け取り方でも注意が必要です。
勤務先によっては、交通費が時給に含まれているケースもあります。
この場合、交通費が別途設定されていないため、パートやアルバイトで得た収入は、そのまま年収や所得として換算される仕組みです。
103万の壁や106万の壁では、収入の計算に交通費を含めないので、別途交通費として支給された方が多く働けるのです。
扶養範囲内で働きたい場合は、交通費が別になっているか確認してから企業探しをするようにしてみてください。
今回は、扶養と交通費の関係性について解説してきました。
扶養内で働き続けたい場合は、交通費を含めた年収が130万円を超えなければ社会保険に加入せずに済みます。
103万や106万の壁には、原則として交通費は含まれません。
しかし、時給に交通費が含まれている場合は注意が必要です。
企業によって交通費の取り扱いには違いがあるので、企業選びの段階で確認しておきましょう。
ヴェルサスでは、様々な求人をご紹介しています。
扶養範囲内で働ける企業のご紹介もしているため、お気軽にご相談ください。