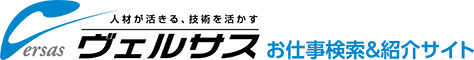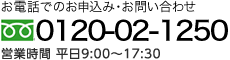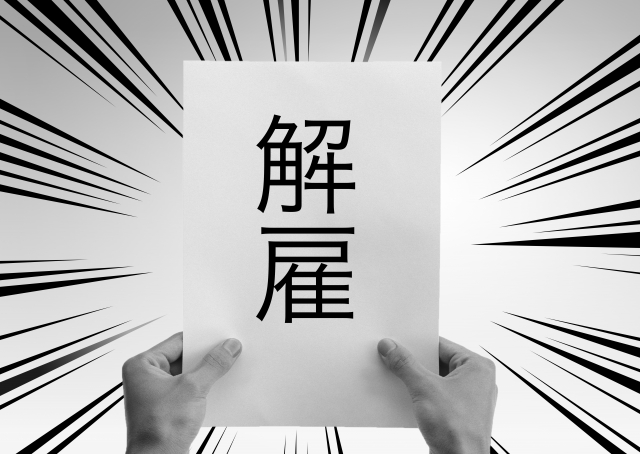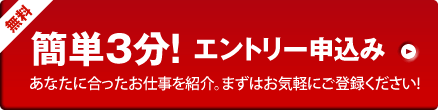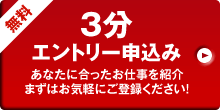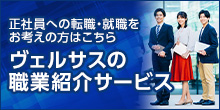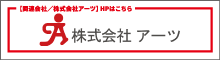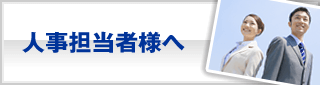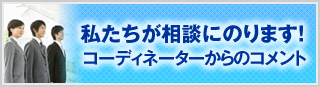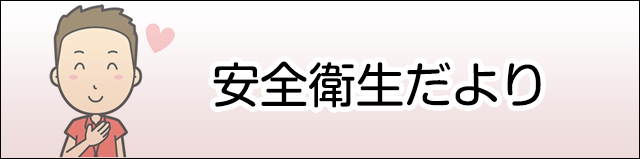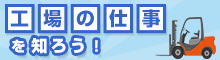こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
近年は結婚後、専業主婦にならず共働きで生活を支える女性がほとんどです。
そんな中で妊娠が発覚した場合、アルバイト・パートなどの非正規雇用だと「産休・育休は取れなさそうだから、仕事を辞めるしかない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、実際にはパートを含む有期雇用労働者の休業取得要件が緩和され、パートでも産休・育休を取得しやすくなっています。
そこで今回は、パートでも産休・育休を取得できるのか、取得するための条件や取得できなかった場合の対応についてご紹介します。
■パートも産休・育休を取得することは可能?
結論から言えば、パートでも産休・育休を取得することは可能です。
産休は出産準備に入る産前休業と、出産後に体力を回復させるための産後休業の2種類があり、出産する本人は入社時期や勤務時間などに関わらず、誰でも取得できるものです。
産休の期間は、産前だと出産予定日の6週間前から任意で取得でき、産後は出産翌日から8週間の取得が義務付けられています。
一方、育休は原則子どもが1歳を迎えるまで育児に専念するための休業制度です。
原則1歳を迎えるまでになりますが、保育所に入所できなかったり、親の妊娠・別居などを理由に育児が困難だと判断されたりした場合は、1歳6ヶ月または2歳になるまで延長可能です。
■パートが産休・育休を取得するための条件
産休は上記でもご紹介したように、出産する本人であれば誰でも取得できるため、パートなどの雇用形態に問わず取得できる休業制度です。
しかし、育休に関しては取得するために条件を満たさなくてはなりません。
育休の条件は以下のとおりです。
子どもが1歳6ヶ月(1歳半~2歳の育児休業の場合は2歳)に達する日までに、労働契約(更新する場合は更新後の契約)期間が満了し、更新されないことが明らかではないこと
簡単に言えば、育休を取得できるのは子どもが1歳6ヶ月を迎えるまで、雇用が見込まれる人です。
有期雇用となるパートの場合、育休期間中に期間満了を迎えてしまう場合でも、契約更新をしないことが明らかでなければ育休を取得できます。
ただし、企業と労働者を代表する人で労使協定が結ばれている場合、以下に該当する労働者は育休を取得できなくなってしまいます。
・雇用期間が1年未満の労働者
・申し出から1年以内に雇用関係の終了が明らかになっている労働者
・週の予定労働日数が2日以下の労働者
■育休を取得できなかった場合の対応
基本的に上記の条件に該当していなければ、パートでも育休は取得できるものです。
しかし、中には育休の取得条件をクリアしているにもかかわらず、会社から育休取得を断られてしまう場合もあります。
その場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか?
・人事または会社の相談窓口に相談する
大手企業を中心に、相談窓口が設けられている場合もあります。
直属の上司が育休に関する知識に乏しく、取得を断ってきた際には、会社の相談窓口に相談すると上司に掛け合ってもらうことも可能です。
その結果、育休の取得を認めてもらえるでしょう。
ただし、会社の相談窓口は大手企業に多く設置されているものの、中小企業では設置されていないケースも少なくありません。
そのような場合は人事担当者に直接相談してみましょう。
・就業規則を確認する
育休が認められなかった際には、会社の就業規則を今一度確認し、社内の規則がどうなっているか、労働協定はどのように記載されているかを確認することが大切です。
育休を取得できない場合、上記でも紹介した対象外に含まれている可能性があります。
きちんと育休を取得できる条件を満たしているかどうか、よく確認しておきましょう。
・労働基準監督署に相談する
労働基準監督署とは、労働基準法や労働安全衛生法などに基づき、労働者の就業環境や安全の確保を整えるための出先機関です。
労働基準監督署では育児・介護休業法に則った紛争解決援助を提供しており、育休取得に関してトラブルが発生した際に相談できます。
労働基準監督署は労働者と事業主の双方から話を聞いた上で、問題の解決に必要な提案・指導を行ってくれます。
育休取得について会社側とトラブルになってしまった際には、労働基準監督署に相談してみましょう。
■パートが産休・育休を取得する際のポイント
円滑に産休・育休を取得できるように、以下のポイントを押さえておきましょう。
・職場には早めに伝える
産休・育休を取得するとなると、その分職場では人員が不足した状態になります。
欠員を補充するにも時間がかかってしまうため、産休・育休を取得する際には職場に早めに伝えておくと良いでしょう。
産休申請のタイミングとしては、妊娠5ヶ月目頃に相談し、出産予定日を迎える1ヶ月前に申請手続きに入るのがおすすめです。
なお、妊娠時の体調は人によって異なります。
そのため、自分が体調的にもベストだと思えるタイミングで職場に伝えるようにしましょう。
・申告期限や手続きについて確認しておく
職場に産休・育休を取得することを伝えたら、申告期限や手続きの方法を確認しておくことも大切です。
産休申請書は企業が年金事務所などに提出する必要があるため、提出期限は産前産後休業の期間中、または産前産後休業が終了した日から起算して1ヶ月以内に提出しなければいけません。
提出が必要な書類は早めの提出を心がけておくと、慌てずに済むでしょう。
・細かい部分まで丁寧な引き継ぎを心がける
パートだからと言って業務の引き継ぎをしっかり行っていないと、産休・育休の期間中に職場が混乱してしまう恐れもあります。
周りの人に迷惑をかけないためにも、自分が行っていた仕事について、細かい部分まで丁寧な引き継ぎを心がけてください。
なお、引き継ぎをしっかり行っておくと、育休後の職場復帰もしやすくなります。
今回は、パートでも産休・育休を取得できるのか解説してきました。
産休は雇用形態に関係なく、出産する本人なら誰でも取得可能となりますが、育休に関しては条件を満たしていないと取得できないので注意が必要です。
就業規則などを改めて確認し、自分が育休を取得できる条件を満たしているかチェックしておきましょう。
関東各地でパート・アルバイト・派遣の求人探しをお手伝いしているヴェルサスは、育休制度や福利厚生が充実した求人情報も多数取り扱っています。
一人ひとりのご要望に合わせて最適な求人情報をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。