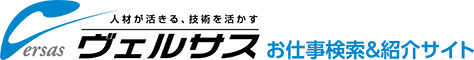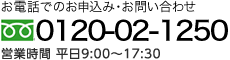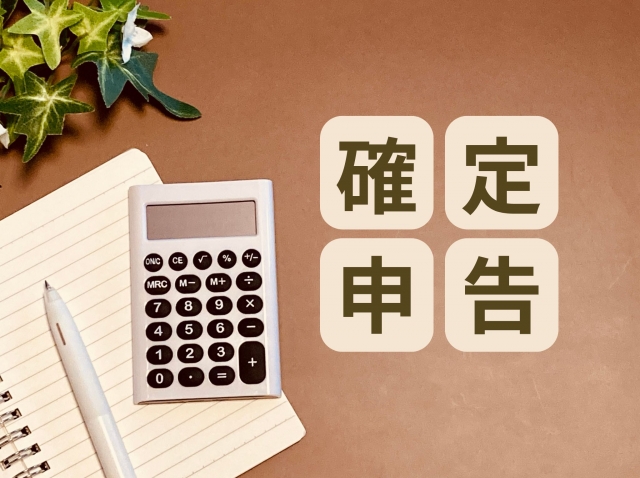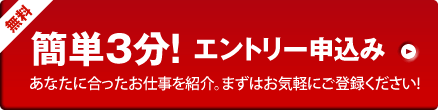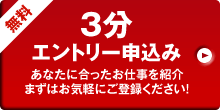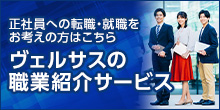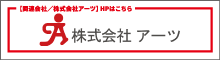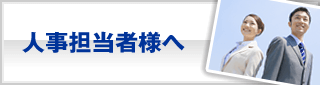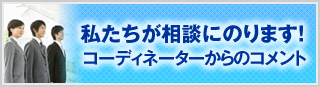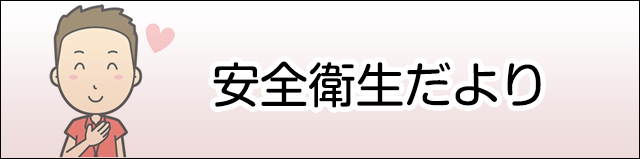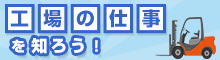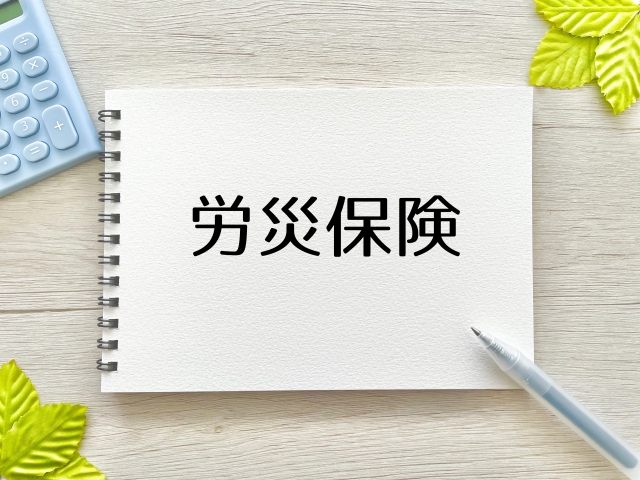
こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
通勤中にケガをしたり、業務が原因で病気になったりした場合、「労災」と認められれば、補償を受けることが可能です。
しかし、労災保険は正社員だけでなく、アルバイトも対象になるのでしょうか。
今回は、労災保険とはどのようなものか、アルバイトにも適用されるのかといった疑問にお答えします。
また、労災保険の手続きの流れや注意点も解説するので、ぜひ最後までお読みください。
■労災保険とは?アルバイトにも適用される?
労災保険とはどのようなものか、アルバイトにも適用されるのか、気になる疑問にお答えします。
・労災保険とは?
労災は「労働災害」の略称です。
労災保険とは、労働者が業務中や通勤時の出来事によって、ケガや病気、障害を負ったり、万が一死亡したりした際に様々な給付金を受け取ることのできる保険制度です。
労働災害により傷病を負った場合、労働者は労働基準監督署から「労災認定」を受けることで、制度を利用できます。
労災保険は雇用側である事業主に対し、加入が義務付けられており、保険料も全額事業主が負担します。
・労災保険はアルバイトにも適用される!
労災保険は、全ての労働者に対し適用されます。
雇用形態は関係ないため、アルバイトやパートも業務中や通勤中に何らかの傷病を負った場合、労災保険の対象となります。
ただし、アルバイトが労災保険を受けるには、「働いている企業が労働保険に加入している」「ケガや病気の原因が業務上のものである」、これらの条件を満たす必要があります。
・労災保険の対象外になることも!
労働災害として認められるには、ケガや病気などの原因が「業務災害」と「通勤災害」のいずれかに当てはまる必要があります。
業務災害は業務中に発生したケガや病気のことで、仕事が原因で発生したケガや病気も含まれます。
一方、通勤災害は通勤中に起こった事故などでケガや障害を負うことで、通勤災害と認められるには、労働者災害補償保険法で定められた通勤要件を満たしている必要があり、通勤経路を遠回りした場合は認められません。
■アルバイトが労災保険から受け取れる補償とは?
労災保険は、業務中や通勤中に起きたケガや病気などを負った労働者の補償を目的としています。
以下では、労働基準監督署から労災認定が適用された場合に給付される主な保険金をご紹介します。
・療養給付金
業務中に発生したケガや病気の治療を無償で受けることができる制度です。
病院での治療費をはじめ、薬代や治療に必要な器具を購入する費用も補償されます。
労災指定病院で治療を受ければ、窓口で治療費を支払う必要はありません。
ただし、労災指定病院ではない場合、いったんは労働者が立て替え、後日立て替えた分の金額を受け取ります。
・休業補償金
治療によって仕事を休む場合、休業中の収入を補償する目的で補償金が支払われます。
補償の対象となるのは、事故発生から一定期間ですが、労働者の平均賃金のおよそ6~8割程度が受け取れます。
・障害給付金
労災によって障害が残った場合に障害年金、もしくは障害一時金が支払われます。
どの程度給付されるかは、障害の内容や後遺症の程度によって異なります。
・遺族給付金
労働災害によって死亡した場合、遺族に対して遺族年金、もしくは遺族一時金が支払われます。
遺族の生活を支援することが目的であり、支給される金額は亡くなった労働者の収入から計算します。
・傷病年金
労災で負った傷病が療養から1年半経過しても治癒しない場合、傷病の程度によって傷病年金が支給されます。
■労災保険を受け取るまでの流れ
労災保険の給付を受けるには、労働基準監督署から労災であると認定を受ける必要があります。
以下では、労災保険を受けるための手続きや流れをご紹介します。
①労働基準監督署に請求書を提出
請求書は会社を通じて提出するほか、労働者が自分で提出することも可能です。
請求書には、傷病を負った従業員の氏名をはじめ、発生日やケガや病気の状態や部位、受診した医療機関などの情報が必要です。
②労働基準監督署による調査
請求書を提出すると、労働基準監督署長より、労災に該当するかどうか、調査が行われます。
労災に認定されれば保険給付を受けることができますが、該当しないと判断されることもあります。
もし、不支給決定に不服であれば、管轄の労働局に対して審査請求をすることが可能です。
③労災保険の給付金が支払われる
ケースによっては時間がかかることもありますが、労働災害に該当すると認定されれば、給付金が支払われます。
■アルバイトが労災保険を受ける際の注意点を解説!
最後に、労災保険を受ける際に気になるポイントや注意点を解説します。
・掛け持ちや副業をしている場合どうなる?
掛け持ちなどで複数の会社でアルバイトしている場合、労災保険の給付基礎日額は、全ての勤務先から受け取る給料の合計金額に基づいて算出されます。
労働災害が発生したのはA社であったとしても、労災認定は全勤務先の業務負荷を総合的に判断して行われます。
・被害者であっても過失があれば減額される
通勤中にお店の看板が倒れてきてケガをした、仕事中に客から暴行を受けたなど、第三者の不法行為によって労災が発生した場合、その相手に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
ただし、被害者にも過失があると判断された場合、過失の程度によって減額されることもあります。
・アルバイト先に労災保険の申請を拒否されたら
労災保険の申請は、自分で行うことも可能です。
もし、勤務先が申請を拒否したとしても、諦める必要はありません。
書類を提出時に勤務先に必要事項の記入を拒否された旨を申告することで、書類に空欄があっても申請を出すことが可能です。
今回は、アルバイトの労災保険事情について解説しました。
労災保険は雇用形態に関係なく、加入が義務付けられています。
勤務中や通勤中に何らかの事故にあいケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合は、労災保険の補償を受けることが可能です。
ヴェルサスでは、様々な職種・業種のお仕事を取り扱っています。
最短3日でお仕事を紹介することもできますので、お仕事探し中の方は、ぜひヴェルサスまでご相談ください。