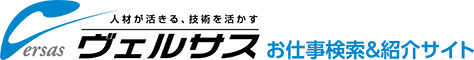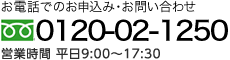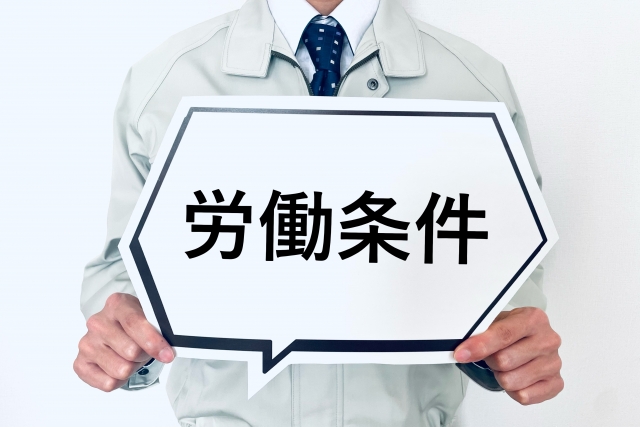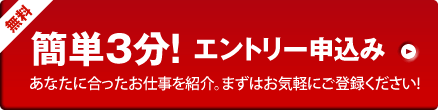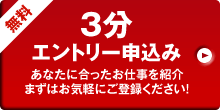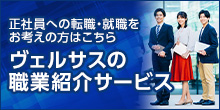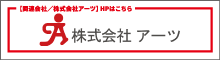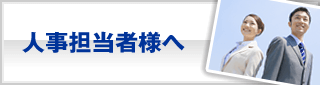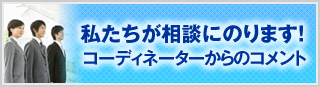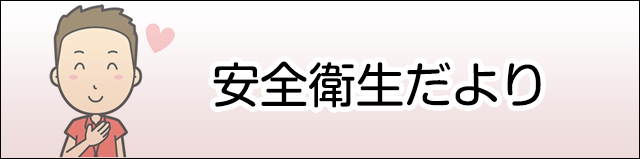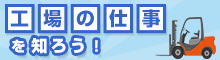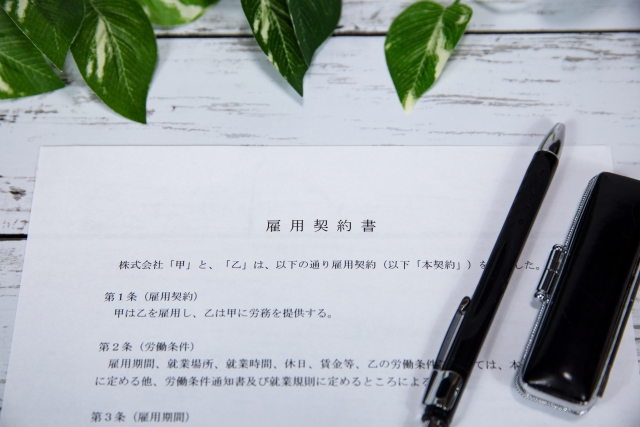
こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
働く時、企業と従業員が雇用契約を行うことを知っていますか?
雇用契約書を交わしたことで、企業と従業員間でのトラブルを未然に防げる可能性がありますが、雇用契約書を必要とする従業員はいるのか、作成時や内容などに注意すべき点などはあるのでしょうか?
この記事では、アルバイトの場合に雇用契約書が必要かを考えると共に、作成時の内容や注意点なども含めてご紹介します。
■雇用契約書とは?
雇用契約書は、どのような内容の書類でしょうか?
雇用する側と労働者の意見や内容が一致した際に書く書面であり、内容は働く際のルールが記載されます。
契約期間、業務内容、始業や終業などの勤務時間、休憩時間、休日、休暇、賃金などの内容が記載されていて、双方でこれらの条件や待遇について相違ないと判断した時に交わされるのです。
記載内容を確認し、それぞれが署名と捺印をして契約が成立する流れです。
雇用側が一方的に条件を押し付けるなどの意味はなく、お互いにこれらの条件を守りましょうという意味合いも込められています。
■雇用契約書はアルバイトでも記載すべき?
雇用契約書は、アルバイトでも作成するべき書類なのでしょうか?
正社員と異なるので、アルバイトにはこのような書類の必要性を感じにくいかもしれません。
そもそも、雇用契約においての解釈は、民法上合意だけで契約が成立できる「許諾契約」に該当し、書面での交付を義務づけていません。
そのため、雇用契約では当事者同士がお互いに合意している状態なら雇用契約が成立します。
しかし、正社員を雇う際に雇用契約書を作成するのは長期的な雇用を目的としていることが多く、今後の労働トラブルを防ぐために書類にしているケースがほとんどです。
■必要なのは労働条件通知書
雇用契約書がない状態では不安に感じてしまいますが、本当に必要になるのは「労働条件通知書」です。
労働条件通知書は労働基準法15条1項、同施行規則5条4項で義務付けられているもので、雇用する際に労働者に対して従事する業務内容、労働時間、賃金などの条件を雇用主が労働者に書面で通知しなければなりません。
労働条件は、労働者の生活を変えてしまう事柄であるほど重要な内容です。
雇用契約締結前に労働条件を提示しなければならず、トラブル防止のためにも書面の交付が原則となっているのです。
ただし、労働条件通知書は雇用主が明示した条件で労働者が合意したことが証明できるものではありません。
お互いに「言った」「言っていない」などの相違を防止するには雇用契約書を交わす方が安心でしょう。
労働条件通知書と雇用契約書を用意するのが大変な場合は、これらを兼ねた書面の作成をして労働者に交付するのも可能ですが、記載事項に関しては細かなルールも決まっているので確認しておくと間違えにくいです。
■アルバイト用の雇用契約書の書き方
雇用契約書の記載事項に関して、正社員とアルバイトで分けられていることがありません。
しかし、アルバイト向けの記載事項もあります。
以下の内容を参考にして作成してみましょう。
【記載義務が生じるもの】
(※労働基準法15条1項後段、同施行規則5条3項)
・就業場所
・業務内容
・労働契約期間
・始業、終業時刻
・所定労働時間を超過する労働の有無
・休憩時間、休日、休暇、交替勤務の場合など就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算、支払いの方法
・賃金支払い日
・昇給に関する事項
【必要性に応じて記載した方が良い内容】
・各種手当
・休職に関する事項
・労働者に費用負担が発生するもの
・安全衛生関連
・職業訓練関連
・災害補償および業務外の傷病扶助
・表彰および制裁
また、これらの他に採用期間に関する事項(期間延長や短縮など)、社会保険に関する事項(一定の条件を満たした場合の加入など)、服務規律に関する事項(懲戒処分の条件や種類)などの記載をしておくと良いでしょう。
【アルバイト特有の記載事項】
(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律6条1項、同施行規則2条1項)
・昇給の有無
・賞与の有無
・退職金の有無
・相談窓口
【2024年4月以降、記載必須事項】
・就業時間、業務内容の変更範囲(変更が想定される場合のみ)
・契約期間、更新回数の上限の内容や有無(期間を定めた雇用の場合)
■雇用契約書に関して注意すべきポイントは?
アルバイトとして働く場合、トラブルを少しでも避けるために以下の内容に注意して記載しましょう。
・記載内容はよく確認する
雇用契約書を作成する目的は、お互いに合意した労働条件で働くことです。
これらの条件を労働者に確認させる、労働者側にわからないことを質問させるような場合、その場で理解するのは難しいかもしれません。
雇用側と労働者の間でトラブルを起こさないためにも、雇用契約書を交わす際には雇用側から説明をしてもらったり、自身で落ち着いて理解するための時間をもらったりしましょう。
認識の違いはトラブルのもとになるので注意してください。
・短期や試用期間でも作成してもらうこと
アルバイトの場合、短期アルバイトになってしまう可能性もあるでしょう。
このような場合でも、労働条件通知書の交付が必要なので雇用契約書についても作成してもらうと安心です。
短期間であっても雇用側と労働者という関係性になるのは変わりません。
書類の交付によってお互いに安心できる関係が築けます。
・正社員と不合理な差がないか確認する
労働条件の内容は労働基準法の規定違反にならない限り、自由に設定できますが正社員とアルバイトの間に不合理な差が設けられていないか確認しましょう。
ただし、アルバイトに簡単な作業をさせる場合や正社員より勤務時間が短い、能力や経験などで明らかな差がある場合は合理的な範囲で待遇が異なっていても問題がありません。
アルバイトを雇う場合、雇用契約書の作成は義務ではないものの労働条件通知書がない場合は違法になってしまうので注意してください。
アルバイトを検討していたものの採用時に十分な説明がない、働く意欲があるものの気になる求人が見つからないという場合はお気軽にヴェルサスにお問い合わせください。
ヴェルサスにはプレミアムな求人が豊富なので、条件を叶える職場に出会える機会も増えるでしょう。