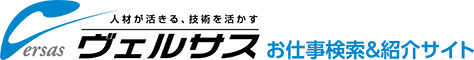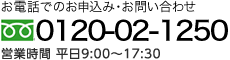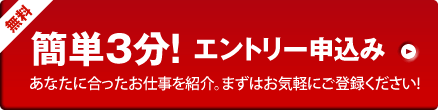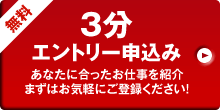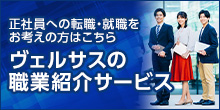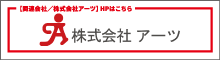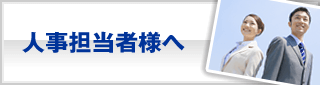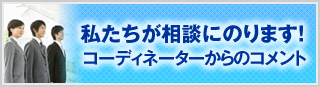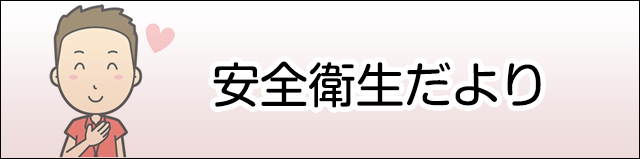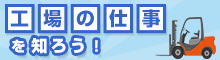こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
パートで働いている時に給与明細を受け取りますが、記載されている項目や金額について疑問を抱く方もいるでしょう。
ここでは、給与明細で控除される内容について詳しく解説していきます。
■給与明細で控除される項目
給与明細には、様々な支給項目もあれば控除項目も記載されています。
支給項目に関しては分かりやすいものの、控除項目はどうやって金額が算出されているのか、なぜ控除されるのかという疑問を抱く方もいるでしょう。
給与明細の控除項目には、法定控除と法定外控除というものがあります。
【法定控除】
・住民税
・所得税
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
【法定外控除】
・財形貯蓄
・社内預金
・労働組合費
・社宅費 など
これを見てわかるように、法定控除には給与から控除する必要があると法律で定められているものであり、法定外控除は会社などで給与から控除する必要がある項目です。
■控除項目について
続いて、控除項目についてみていきましょう。
・住民税
住民税は、前年度の所得に対して控除されるものです。
1月1日に住所がある都道府県、市区町村に対して税金を納めます。
均等割と所得割があり、給与が93万円~100万円程度のパートなら非課税扱いになります。
年収100万円が境界ラインであり、これを上回ると数千円程度の住民税が必要です。
・所得税
所得税は、個人の所得に対してかかってくる税金です。
年間103万円以下であればパートでもバイトでも引かれます。
これは個人にかかってくる税金であり、収入に応じて金額が変わってくるものです。
給与収入にかかってくる所得税を会社が予め天引きし、それを個人に代わって国に納める仕組みです。
所得税は、社会保険料等控除後の月収が88,000円以上で自身が扶養している親族がいない場合に源泉徴収されます。
ただし、パート先がひとつであれば年末調整で正しく所得税の計算をし直せますが、パート先を掛け持ちしている場合は確定申告を行い、正しい所得税の確定が必要です。
・社会保険料
パートでも一定の条件を満たしている場合、社会保険への加入が必要です。
社会保険は、主に健康保険と厚生年金保険を指していて、2024年の改正によって1週間に20時間以上、月収88,000円以上であることなどが含まれ、適用範囲も広がりをみせています。
他にも2ヶ月以上の雇用期間の見込みがあり、従業員数が101人以上、学業を主とする学生でない場合は加入の必要があります。
社会保険には健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険なども含まれています。
・厚生年金保険
厚生年金保険は、会社員や公務員などが加入する公的年金制度です。
厚生年金保険は会社と労働者が半分ずつ負担して支払います。
パートの場合は、1週間の所定労働時間、1ヶ月の所定労働時間の両方が正社員の3/4以上が加入条件です。
しかし、短時間労働者のパートでも社会保険の適用拡大によって会社の従業員数に従って加入しなければならないケースもあります。
・介護保険料
介護保険料は、介護が必要になった高齢者に対して社会全体で支える仕組みを持つ制度です。
40歳以上65歳未満の被保険者が加入対象です。
介護保険料に関しては正社員もパートも関係なく徴収されます。
パートで働いているものの、配偶者の扶養となっている場合は配偶者加入の健康保険から加入する仕組みです。
介護保険料は、65歳以上の要介護または要支援認定を受けている人に対して給付し、訪問介護などの適切なサービスが受けられるようにサポートする目的があります。
・雇用保険料
雇用保険は、失業時や病気やケガで働けなくなった場合に国から受けられる公的保険制度です。
1週間の所定時間が20時間以上、31日以上の継続雇用が予定されている場合に加入する必要があります。
雇用保険は、会社と労働者が法律で決められた割合を負担して支払います。
失業予防や労働者の能力開発、労働者の福祉増進などの目的で使用されます。
■パートで手取りが少ない時に確認したいポイント
パートで働いているのに手取りが少ないと感じた場合は、税金や社会保険料の負担が発生しているからです。
これらの負担は年収によって変わってきます。
ここでは、社会保険の金額についてみていきましょう。
・雇用保険
失業した際に給付を受け取れます。
パートの負担分は賃金の0.3%です。
・健康保険
健康保険は、ケガや病気などで病院に行った際の医療費負担が軽減されるものです。
パートの負担分は、標準報酬月額の4~5%程度です。
ただし、保険料率は加入している健康保険によって異なります。
・介護保険
介護サービス利用時の負担が軽減される保険です。
加入は40歳~65歳で、標準報酬月額の0.8~0.9%です。
健康保険と同様に、保険料率は加入する保険によって異なるので注意してください。
・厚生年金
65歳以上や障害認定を受けた際に年金が受け取れる制度です。
パートの負担分は、標準報酬月額の9.15%程度になります。
社会保険の場合、条件を満たしていれば強制加入となります。
保険料が天引きされることを知らずに働いている場合、これまでの月収よりも金額が少なくて驚くかもしれません。
上記の内容を参考にして、保険料を引かれても以前と同じくらいの収入が欲しい場合にはどれくらい働くべきか考えてみましょう。
■控除の仕組みを考えて働いてみよう
控除される内容に応じて、数万円の収入の差で加入しなければならない制度がいくつもあります。
簡単に住民税は100万円、所得税は103万円、社会保険は月額賃金88,000円などの条件になります。
これは一定の金額ではなく、段階ごとに加入の条件が変わってしまうので、事前にこのラインを超えると控除されることを念頭に置きつつ、働く時間を考えてみましょう。
今回は、パートの給与明細にある控除が何かに加えて、項目や金額、加入条件などを解説してきました。
それぞれ控除される項目によって目的が異なるだけでなく、収入が増えることで税金の支払いも生じます。
パートといえど、働くことで一時的に収入が減ってしまうように感じやすいので、働く際にはこれらの控除を踏まえて働く時間を考えてみましょう。
ヴェルサスでは、派遣で働く際にはこれらの内容を詳しく説明し、さらに確定申告などの際にもサポートいたします。
税金や控除を把握した上で働きたい方は、お気軽にヴェルサスにご相談ください。