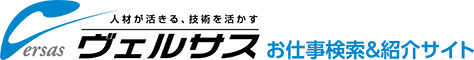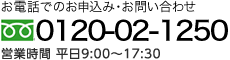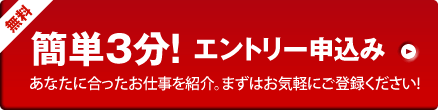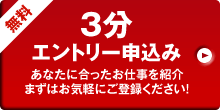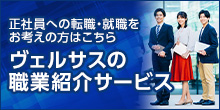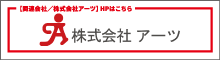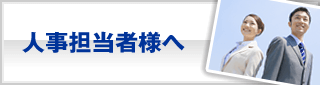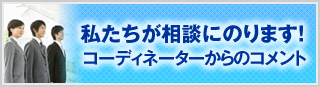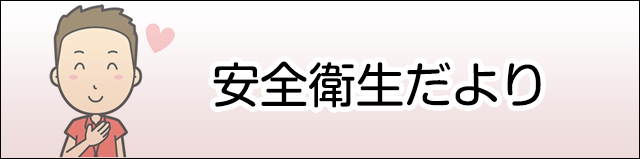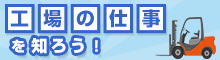こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
どんなに気を付けていても、勤務中に事故やケガをしてしまうことがあります。
勤務中に事故やケガをしてしまった場合、自分で治療費を負担しなければならないと考えるかもしれませんが、勤務中のケガは内容によって労災認定されることがあります。
もし、労災と認定されれば実費で支払うことはありませんが、派遣スタッフの場合も同じでしょうか?
この記事では、派遣スタッフが業務中にケガをした場合の方法や手続きに関して解説します。
■そもそも「労災」とは?
「労災」は、「労働災害」の略で通勤中や業務時間内に事故やケガをしたり、入院や死亡してしまったりすることを指します。
内容は、労働安全衛生法で定められていて、「建設作業中に荷物が落下してケガをした」「工場で大型の機械に巻き込まれて入院した」なども対象です。
他にも、「業務過多によって残業が規定時間を超えたことが続き、過労死をした」「職場でのパワハラが原因で精神的な疾患となった」なども、労災が認められる可能性があります。
このような事態になった時、「派遣スタッフだから労災の対象外」と考えるかもしれません。
しかし、業務内容や職種に関係なく業務時間帯や通勤時間中に起こったケガや病気などは労災に該当する可能性があります。
企業は、雇用形態に関係なく従業員が1人でもいる場合は労災を保障する義務があり、「労災保険(労働者災害補償保険)」を負担しているのです。
■派遣社員の労災は支払われる?対応はどこがする?
上記でも説明したように、労災は雇用形態に関係なく該当した以上支払う義務があります。
しかし、派遣社員が派遣先でケガをした場合は、派遣元か派遣先のどちらが負担するのでしょうか?
まず、派遣社員の場合は派遣会社が労働者を雇って派遣先で勤務させている状態です。
労働者に業務を指示するのは派遣先となりますが、労働基準法や労働安全衛生法では派遣元が責任を負うことになります。
簡単に言えば、業務をしていてケガをしたとしても雇っているのは派遣元なので責任も派遣元になる仕組みです。
ただし、労働派遣法では特例として「労働者派遣の実態から派遣元事業主に責任を問いえない事項」「派遣労働者の保護の実効を期する上から派遣先に責任を負わせることが適当な事項」に該当する場合は派遣先の責任となります。
このような特例に該当するのは、派遣先の安全管理に問題があった場合が多いでしょう。
■労災認定や給付までの流れについて
派遣スタッフが業務中にケガをした場合、労災と認定されるのは個人で決めることではありません。
以下の流れを参考にしてみましょう。
①病院を受診する
通勤中や業務中にケガや病気を発症した場合は、病院に受診しましょう。
後遺症などの発生や深刻な症状になる前に速やかに受診し、その際にはできる限りの範囲で派遣元に労災発生の報告を行います。
報告時には「労災が起こった日時、場所」「労災に遭った労働者の氏名」「発生状況」「労災に遭った従業員の症状や状態」などです。
労災の場合は、健康保険が適用されないので一般的な医療機関を受診したり入院したりした場合でも一度全額負担になります。
労災病院や労災指定病院では、使用する労災申請書類が異なります。
②派遣元から証明を出してもらう
労災の発生を申告した場合、申告書作成や手続きなどは本人ではなく派遣元が実施します。
労災の事実を認めてもらえない、退職後で手続きしてもらえないという場合は、直接労働基準監督署に行って申請しなければなりません。
労災は発生して時間が経過していても給付申請可能ですが、補償内容によって事項が異なるので注意してください。
労災の給付に関しては、給付申請書を作成して所轄の労働基準監督署に提出します。
◎休業給付、療養給付、介護給付、葬祭給付、二次健康診断等給付:時効2年
◎障害給付、遺族給付:時効5年
③労災事故調査と保険給付
労災が発生し、申請が行われた場合は労働基準監督署が調査を行います。
労災に遭った労働者本人、その関係者の両者に対して必要に応じて状況を確認したり書類を提出してもらったりします。
調査結果で労災認定がされた場合は、指定口座に給付金が振り込まれる流れになっています。
ただし、労災発生直後すぐに給付金の支払いは行われず、少し時間が経過してからになります。
できるだけ早く派遣元や労働基準監督署に報告するのが良いでしょう。
■派遣社員が覚えておきたい労災基礎知識について
ここでは、派遣社員が覚えておきたい労災の基礎知識をご紹介します。
◎療養補償給付・療養給付・複数事業労働者療養給付
療養補償給付・療養給付・複数事業労働者療養給付は、通勤中や業務中に生じたケガや病気などの治療にかかる費用を補償します。
指定された医療機関であれば、無償で医療サービスが受けられます。
医療サービスにかかった費用は現金給付として受け取れます。
自身で最寄りの医療機関を選ぶ場合は、健康保険を使わずに労災であることを伝えて受診し、費用請求書を労働基準監督署に提出します。
◎休業補償給付・休業給付・複数事業労働者休業給付
休業補償給付・休業給付・複数事業労働者休業給付は、通勤や業務が原因になったケガや病気治療のため、一定期間働けない場合に補償が受けられます。
賃金が受け取れずに生活が困難になった場合の補償で、給付条件として「賃金を受けていない」「労働できない」「業務上の自由または通勤による負傷や疾病による療養のため」という内容に当てはまらなければなりません。
この場合になってやっと給付が受けられます。
◎遺族補償給付・遺族給付・複数事業労働者遺族給付
遺族補償給付・遺族給付・複数事業労働者遺族給付は、労災で労働者死亡などの場合に給付される年金や一時金です。
被災した労働者の配偶者、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹が対象で、基本的には妻以外の遺族は一定の高齢や年少かなど一定の障害が条件です。
労災事故が起こった場合、派遣であろうとパートであろうと関係なく、報告する義務があり、診療代金を請求することができます。
申請された時は労働基準監督署が調査を行い、労災認定されるとお金が戻ってくる仕組みです。
中には、派遣先の上司に労災について相談しにくいというケースもありますが、労働者の権利はきちんと利用しましょう。
ヴェルサスでは、派遣先でも働きやすい環境を整えているだけでなく、困ったことがあれば気軽に相談できる体制を整えています。
派遣について興味がある方は、お気軽にヴェルサスまでご相談ください。