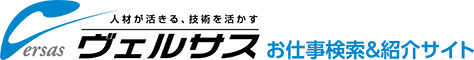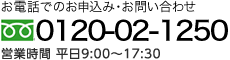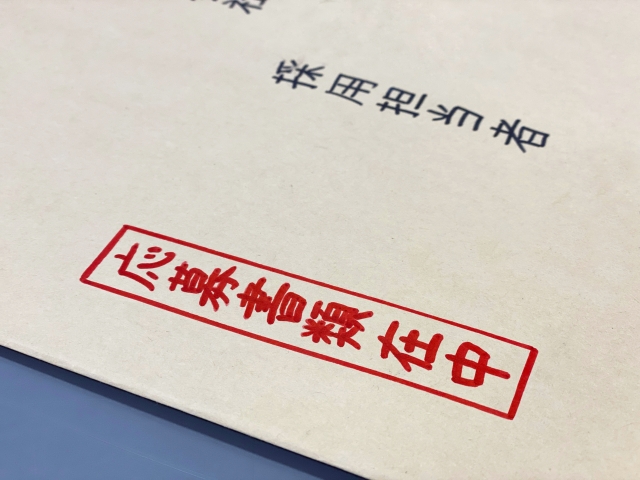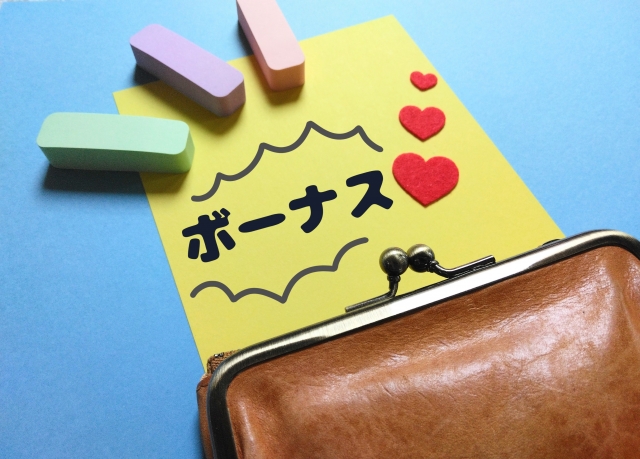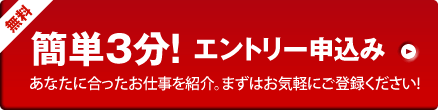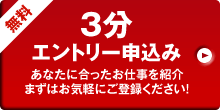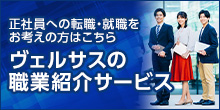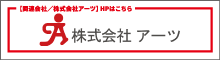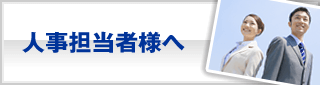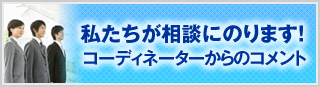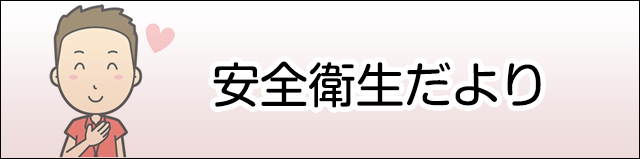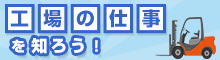こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
2025年4月に育児・介護休業法が改正し、子の看護休暇に関するルールが変更されています。
子どもを抱える従業員の権利となっている制度ですが、「正社員のみの制度なの?」「パートでも取得できるの?」などと疑問に感じている方もいるはずです。
そこで今回は、子の看護休暇の概要について解説すると共に、改正前との違いや時間単位での取得が可能なのか、様々な疑問に迫っていきます。
子どもを持つ方や子の看護休暇について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
■子の看護休暇とは
子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づいて設けられている制度の1つです。
2025年4月に行われた法改正によって、「子の看護等休暇」に名称が変更されています。
子どもが病気や怪我をした際に看護をするために取得できる休暇制度となっており、共働きの世帯が増えたことで、仕事と育児の両立を支援するために導入されました。
【欠勤扱いとはならない】
子の看護休暇を取得するとなれば「欠勤扱いになるのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。
欠勤となれば評価や査定に影響を与えるので不安になるのも仕方がありません。
しかし、子の看護等休暇は育児・介護休業法に基づいて義務付けられた休暇制度です。
そのため、従業員が精度を活用して休暇を申請した場合、事業主が従業員に対して不利益な扱いをすることが「育児法10条・16条の4」で禁じられています。
査定には影響を及ぼさないため、安心して子の看護休暇を取得できます。
【取得できる労働者】
子の看護休暇を取得できる労働者は、正社員だけではありません。
ほぼ全ての労働者が利用できるため、契約社員やパートでも利用可能です。
対象外となる労働者は以下の通りです。
・日雇い労働者
・1週間当たりの所定労働日数が2日以下の従業員
以前は、「雇用期間6ヶ月未満の従業員」も対象外となっていましたが、2025年4月施行の法改正によって除外されました。
これによって多くのパート労働者が対象に含まれるようになっています。
【取得できる日数】
看護休暇を取得できる日数は、子どもの人数によって異なります。
・子ども1人:年間5日
・子ども2以上:年間10日
年度単位で日数が付与される仕組みとなっており、市年度への繰り越しは不可能です。
また、労働基準法の有給休暇とは別枠となっています。
ただし、午前中は子の看護休暇を取得して、午後に有給休暇を取得するといった使い方であれば問題ありません。
企業が独自に日数を増やすことも可能になっているので、働いている場所によっては上記よりも日数が多いケースもあります。
また、時季変更権も適用されていません。
企業の閑散期や繁忙期に応じて休暇取得の可否を調整できる権利を時季変更権と言いますが、子の看護休暇では時季変更権を企業側は持っていないため、忙しい時期だからと看護休暇の申し出を企業は拒むことはできないのです。
これは、子どもの看護の必要性は1年中発生する可能性があるためです。
【取得できるシーン】
子の看護休暇が取得できるシーンとして考えられるのは以下の通りです。
・子どもの体調不良
・子どもの怪我
・子どもの通院
・子どもの予防接種
・乳幼児健診
また、2025年4月の法改正によって、以下のシーンでも利用できるようになっています。
・感染症の流行による保育園や学校の休業
・子どもの入園式
・子どもの入学式
子どもの健康管理だけではなく、育児に関する幅広いシーンで利用できる休暇制度へと変更されています。
【取得できる子どもの年齢】
子の看護等休暇の対象となる子どもは以下のようになっています。
・小学校第3学年終了前(9歳)
具体的には、9歳に達する日以後の最初の3月31日までとなりますが、あくまでも育児・介護休業法で定められた最低条件となっているため、企業によっては9歳以降でも休暇制度の取得を認めているところは存在します。
以前は、小学校就学の始期に達するまで(6歳)となっていたため、法改正によって拡大されています。
【取得できる単位】
子の看護休暇は、2021年1月以前は短くても半日単位でしか利用できませんでした。
しかし、2021年1月の改正によって1時間単位での取得も可能になっています。
また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者の場合は対象にはならなかったため、パート従業員の中には半日での取得ができないケースもあったのです。
しかし、法改正されたことで1日の所定労働時間が4時間以下の従業員でも半日単位での取得が可能になった他、1時間単位での取得もできるようになったため、パートでも数時間の取得が可能となりました。
病院を受診した後に出勤、出勤してから夕方に受診などもしやすくなっています。
■子の看護休暇の取得方法
子の看護休暇の取得方法は、企業によって異なります。
書面での事前申請が必要なケースや社内のオンラインシステムを活用して申請するケースもあります。
しかし、急な発熱や事故、怪我などによってやむを得ずに休むケースは多いはずです。
そのため、基本的には事後申請でも認められます。
また、企業によっては証明書類の提出を求められるケースもあります。
あらかじめルールを確認しておくことが大切です。
注意点としては、証明書類の提出がない時や事後申請であっても、それを理由に子の看護休暇の権利が消滅することがない点です。
育児・介護休業法では、子の看護休暇を理由として従業員が不利益を被ることを禁じているため、「申請を受け入れてくれない」「評価に影響があると言われた」といった場合には、労働局といった機関への相談を検討してみましょう。
今回は、子の看護休暇制度について解説してきました。
子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づく労働者の権利です。
パートでも取得可能となっており、1日単位ではなく半日や1時間単位でも取得できます。
子ども1人であれば年間で5日の取得が可能となっているので、子どもの急な体調不良時や予防接種などをする際には活用を検討してみましょう。
ヴェルサスでは、子どものいる方におすすめの求人を豊富に取り扱っています。
子どもが保育園に行っている間、学校に行っている間のみ働ける職場や急な休みにも対応がしやすい職場など、働きやすい求人を多数ご用意しているので、転職を検討している方は、ぜひヴェルサスで自分に合う職探しをしてみてください。