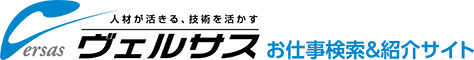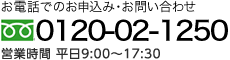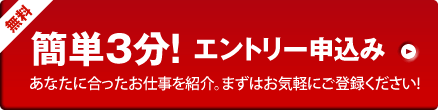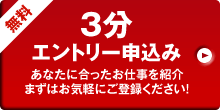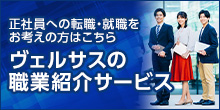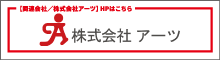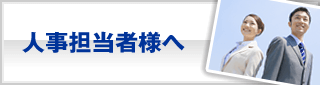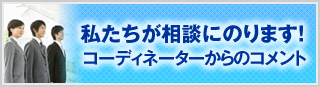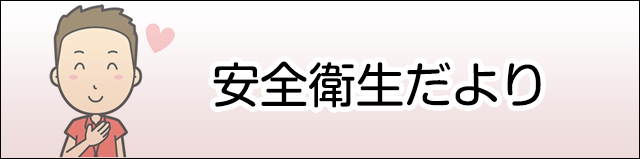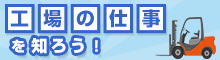こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
皆さんは「雇い止め」という言葉を聞いたことがありますか?
派遣関連のトラブルとして認識されている雇い止めですが、どのような内容なのか理解していない方もいるでしょう。
ここでは、雇い止めが何かに加えて違法かどうかの判断基準についても解説します。
■雇い止めって何?
雇い止めは、派遣元もしくは派遣先企業が有期労働契約者に対して契約期間満了以降の更新を拒否することを言います。
有期雇用契約の場合、契約期間が定められているため期間満了に伴って契約が終了することが原則なので、雇い止めとなっても違法とは認定されません。
本来は、労働契約更新を決めるのは使用者と労働者のお互いにあり、契約期間に決まりがあっても契約更新をするかどうかを一方的に決めることはできないのです。
特に、何度も契約を更新していたことから次回の契約更新に対しても期待していた場合、実質的に期間の定めを持たない雇用契約と同じ状態になった場合などは、雇い止めになる可能性が高いでしょう。
雇い止めと似た言葉として「解雇」というものがありますが、解雇は一方的に企業が契約を打ち切る際に使われます。
■派遣の3年ルールとは違う?
派遣には「3年ルール」というものが存在しています。
3年ルールは、派遣法に基づいたもので同じ派遣社員が同じ事務所で3年以上働いてはいけないというものです。
その理由は、長期間に渡って同じ派遣先にいることで労働者の安定した雇用を侵害する恐れ、同一労働同一賃金のルールを侵害する恐れ、長期間の派遣契約によって契約範囲を超えた業務を任される恐れがあるからです。
このような理由から、1人の派遣社員が同じ事務所、部、課、などに3年以上勤務できません。
もし3年以上働きたいなら、派遣元となる派遣会社で無期雇用契約となっている場合、60歳以上である場合、日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)に派遣する場合、終わる時期が決まっている有期プロジェクト業務へ派遣される場合、産休や育休、介護休暇などの取得により労働者の業務を担当する場合などであれば3年以上派遣社員として雇用継続が可能です。
■雇い止めは契約満了、解雇、派遣切りも違う?
雇い止め以外にも契約満了、解雇、派遣切りなどの言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これらの言葉も、雇い止めと同じような意味で使われているのでしょうか?
・契約満了は契約を更新しない時に使う
有期労働契約期間に基づいて契約が満了した場合、次回の契約が更新されない時に使います。
派遣先企業が契約更新しない場合、契約満了日の30日前までに派遣会社に通知し、その後派遣会社から派遣社員に契約満了であることが通知されます。
派遣社員側も契約更新を希望しない場合は、満了日に退職となります。
「契約満了(解除)」となる場合は、契約期間の途中で契約を打ち切ることです。
・解雇は一方的な意思表示に使う
解雇は、契約期間中に企業側から労働者を一方的な意思表示で辞めさせることです。
有期雇用契約の場合、契約期間中は原則解雇ができません。
その理由は、有期雇用契約である以上期間中は雇用を保障するという意味を含めているからです。
たとえ、やむを得ない理由があったとしても認められるケースはほとんどありません。
・派遣切りは派遣社員との契約終了時に使う
派遣切りは、派遣先の都合で派遣元との労働者派遣契約の打ち切りを意味しています。
派遣切りは特定の派遣社員との契約解除を意味しているのではなく、派遣会社と企業との間での契約切れです。
派遣切りによって派遣先が無くなったため、派遣元が派遣社員の雇用契約を終わらせようとすることもあります。
これによって、派遣社員の雇い止めが起こる可能性もあるでしょう。
■雇い止めが違法になるケースはどんな時?
雇い止めが起こっても、このこと自体に違法性はありません。
しかし、複数回に渡って契約更新を繰り返し、雇用期間も長期に及んでいる場合は実質的に期間の定めが設けられていない雇用契約と同等であり、派遣社員側も契約更新を期待するでしょう。
有期雇用契約は契約期間満了によって終了するものであり、これを理由に契約を打ち切られても雇い止めが違法と判断できません。
企業側が雇い止めを正当化できるのは、客観的に合理的な理由のみとなるので、能力不足、成績不良、病気、ケガなどでの就業不能、ハラスメント、業務命令違反、勤務態度、事業縮小、人員整理などでなければなりません。
ここで、実際に起こった雇い止め無効の判例をみていきましょう。
【判例①:パート従業員の場合】
約7年間雇用されていたパート従業員の判例です。
過去に何度も有期労働契約を講師にしていて、業務内容が正社員と同じであること、就業規則に反して契約更新時に面談が行われていなかったこと、労働期間制限があることを十分説明していなかったこと、更新拒絶の件数が少ないことなどの理由で、企業と従業員間の有期労働契約は実質的に無期雇用契約と変わらないなどの合理的な理由から、雇い止め無効の判断がされました。
【判例②:有期雇用労働者の場合】
約5年半の間に4回にわたって有期労働契約を締結していたものの、その後1年の有期労働契約を締結してから更新の申し込みをすると、拒絶され雇用期間の満了日に雇い止めを通知された事例です。
労働者側はこの雇い止めに対して合理的な理由を欠いており、社会通念上相当と認められない、また労契法18条から向き労働契約に転換されたとして裁判を行いました。
判決では、労働契約を更新しない自由が認められているため、それ自体は不合理ではないとしたものの、雇用継続に対する期待が合理的な理由に基づいているとして、雇い止めの無効が認められました。
また、契約期間が5年以上経過していることから、有期労働契約からの無期転換も認められています。
【判例③:派遣社員の場合】
有期労働契約を交わし、家電量販店で業務を行っていたものの、突然派遣会社から勤務態度などを理由に雇い止めされた事例です。
契約期間は3ヶ月でしたが、有期労働契約は既に5回更新されていました。
5回更新されたことを理由に、契約更新への期待に合理的な理由があると判断されています。
雇い止めをした企業側が主張するような業務上の指示に対する反抗、協調性の欠如、他の従業員への恫喝なども裏づける証拠がないことも雇い止め無効の判断になっています。
派遣社員として頑張って働いている時に雇い止めをされてしまうと、これまでの更新は何だったのかと考えてしまうのも無理はないでしょう。
特に派遣で働いている場合、いつこのような事態に巻き込まれても不思議ではありません。
もし、派遣社員として働いていて納得できないことがあれば気軽に派遣元の担当者に相談してみましょう。
ヴェルサスでは、このような派遣先でのトラブルなども気軽に相談しやすい体制を整えています。
サポートしてくれるスタッフがいるので、お気軽にご相談ください。