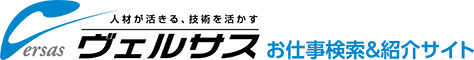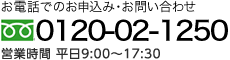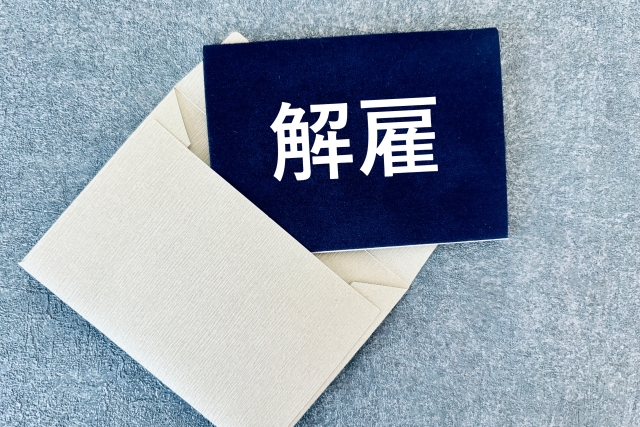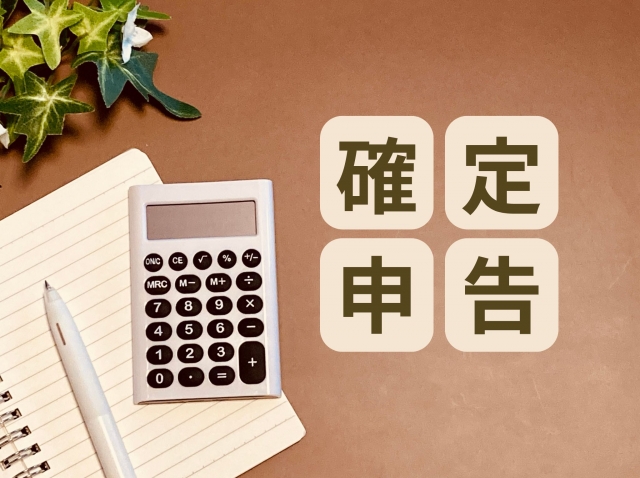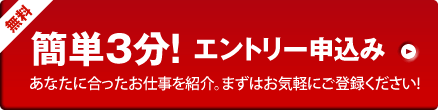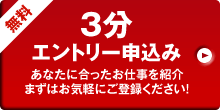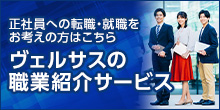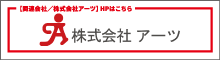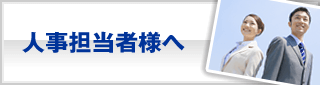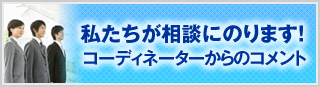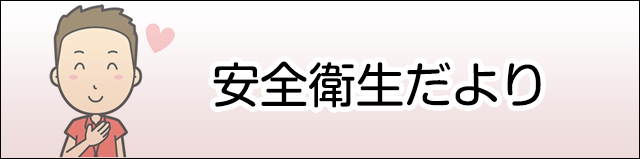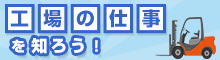こんにちは!ヴェルサスのブログ担当です。
パートで働いており、これから妊娠や出産の予定がある方にとって、産休や育休を取得できるかどうかは気になるポイントの1つではないでしょうか。
特に、雇用保険に加入していない場合、仕事を辞めなければならないのか、気になっている方もいるでしょう。
そこで今回は、雇用保険に加入していないパートでも産休は取れるのか、気になる疑問を解説します。
■雇用保険の加入条件をさらっとおさらい!
雇用保険とは失業した場合などに給付を受けられる保険のことです。
加入すると保険料を支払わなければならないものの、離職した際に求職者給付や就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などを受けることができます。
なお、雇用保険に加入するには、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「雇用契約が31日以上ある」などの条件を満たす必要があるため、パートの場合、加入していない人も少なくありません。
■雇用保険に入っていなくても産休は取れる
結論からいえば、雇用保険に加入していないパートでも産休を取ることは可能です。
産休は出産や育児のために仕事を休む制度のことで、バイトやパート、正社員など雇用形態を問わず、妊婦なら誰でも取得する権利を持っています。
労働基準法でも定められており、雇用保険に加入していないからといって、産休を取ってはいけないなどの制限はありません。
なお、雇用保険に加入していなくても取れる産休には、産前休業と産後休業があります。
以下では、それぞれの特徴を詳しく解説します。
・産前休業
産前休業は、出産前に取得できる産休のことです。
出産予定日の6週間前、双子以上であれば14週間前から取得できます。
ただし、産前休業は任意のため、取得したい場合は自分で申請をする必要があります。
体調や仕事の状況とも相談しながら、決めると良いでしょう。
産前休業の取得を申請しなければ、出産直前まで働くことも可能です。
・産後休業
産後休業は出産後に取得できる産休のことです。
妊娠・出産は女性の体への負担も大きく、回復するまでに相応の時間を要します。
そのため、出産した日の翌日から8週間は母体を保護するため、就業できないと労働基準法によって定められています。
ただし、本人が復職を希望しており、医師も問題ないと認めている場合は、産後6週間以降なら就業可能です。
パートの場合、企業は産後8週間と期間満了後30日間は解雇することはできません。
・育休を取るには条件がある
育児休業とは、原則1歳未満の子を養育するための休業です。
誰でも取得できる産休と違い、育休を取得するには、子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約の期間が終了する見込みがないなどの条件があります。
雇用されてから1年経過していない、週の所定労働日数が2日以下など労使協定の対象外にできる労働者は取得できないため注意が必要です。
なお、育休は条件を満たしていれば男女関係なく取得することが可能です。
■雇用保険に入っていないと産休中は無給になる!
誰でも取得できるものの、一般的に産休中は無給となります。
給与はあくまでも労働の対価として支払われるものです。
働くことのできない産休中は、企業も賃金を支払う義務はありません。
ただし、産休中の給与の取り扱いは企業の判断にゆだねられており、中には休業中の給与を保証しているところもあります。
また、企業によっては福利厚生の一般として金銭的なサポートを行っているところもあり、産休中の経済的負担を軽くすることができるでしょう。
ただし、このような場合、保証するのは正社員などに限定しており、パートは対象外であることもあるためしっかり確認することが大切です。
・雇用保険に加入していないと不利なことも多い!
雇用保険に加入していれば、パートであっても産休や育休中に育児休業給付金などの経済支援を受けられます。
しかし、雇用保険に加入していなければこれらの経済支援を受け取れないため、育休中の経済的な負担が大きくのしかかることになるでしょう。
今後、妊娠・出産する予定がある場合は雇用保険への加入を検討するのも選択肢の1つです。
■雇用保険に入っていなくてももらえるお金
雇用保険に入っていない場合、育休手当は支給されませんが、受け取れる一時金や支援金もあります。
以下では、雇用保険に加入していないパートでももらえるお金について解説します。
・出産一時金
出産一時金は、出産した際に公的医療保険から支給される一時金です。
産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠週数22週以降に出産すれば子ども1人につき50万円、妊娠週数22週未満や産科医療補償制度未加入の医療機関などで出産した場合は子ども1人につき48.8万円が支給されます。
ただし、出産にかかる費用は健康保険の適用外です。
分娩費や入院費は全額自己負担となるほか、申請するには手続きが必要です。
直接支払い制度を利用すれば手続きを簡略化できるため、出産する医療機関に対応しているか確認してみると良いでしょう。
・子育てクーポン等
出産に対しお祝い金や奨励金、子育てクーポンなどを支給している自治体もあります。
子どもの人数や年齢に応じて祝い金を支給したり、3人目以降の子ども1人につき奨励金を支給したりと支援の内容は自治体によって異なります。
中には水道料金を助成したり、子育て応援パスポートを発行したりしているところもあります。
自治体の行っている支援は雇用保険関係なく受けることができるため、住んでいる自治体の案内などを確認することをおすすめします。
今回は、雇用保険に加入していないパートでも産休は取れるのか、詳しく解説しました。
雇用保険に加入していなくても、産休を取ることは可能です。
ただし、雇用保険に加入していない場合、育児給付金をもらえないなど支援内容に大きな差が生まれるため注意が必要です。
ただし、育児給付金がもらえなくても、住んでいる自治体によっては様々な支援金や制度が用意されているため、気になる方は自治体のホームページや案内を確認することをおすすめします。
ヴェルサスでは、幅広いお仕事の中からあなたに合った求人を紹介します。
転職活動のサポートも行っていますので、興味のある方はお気軽にお問合せください。